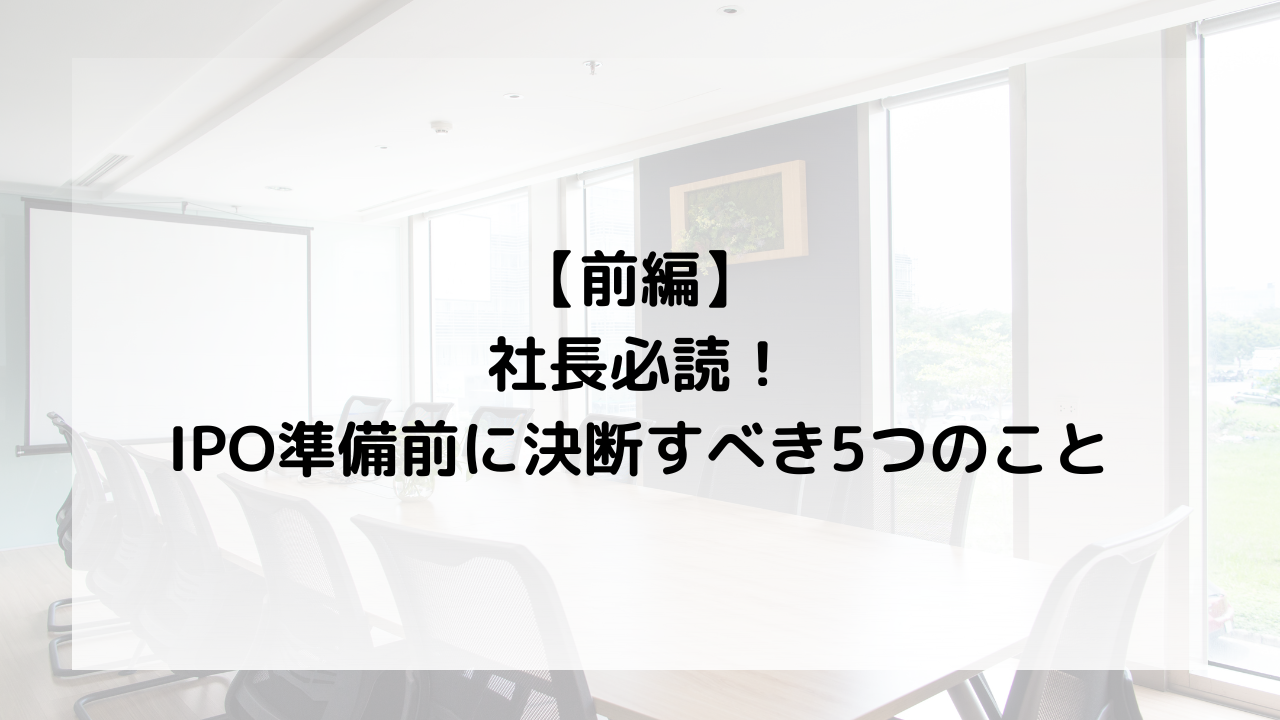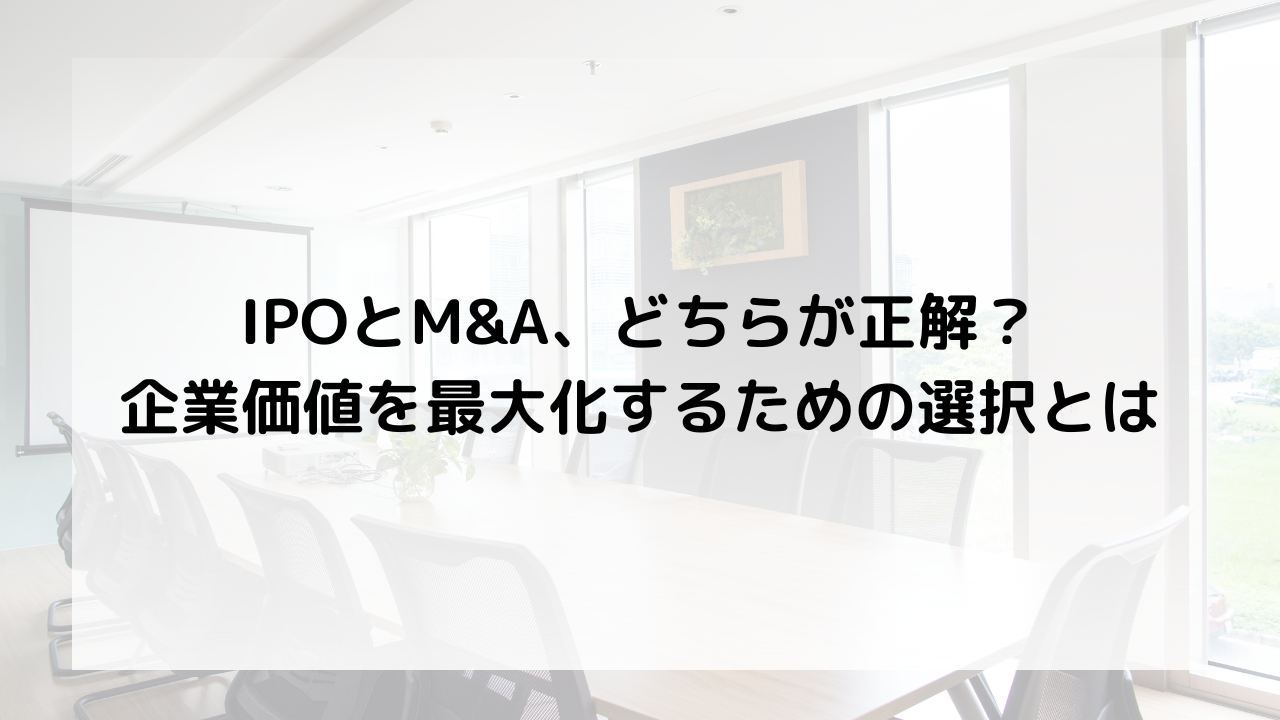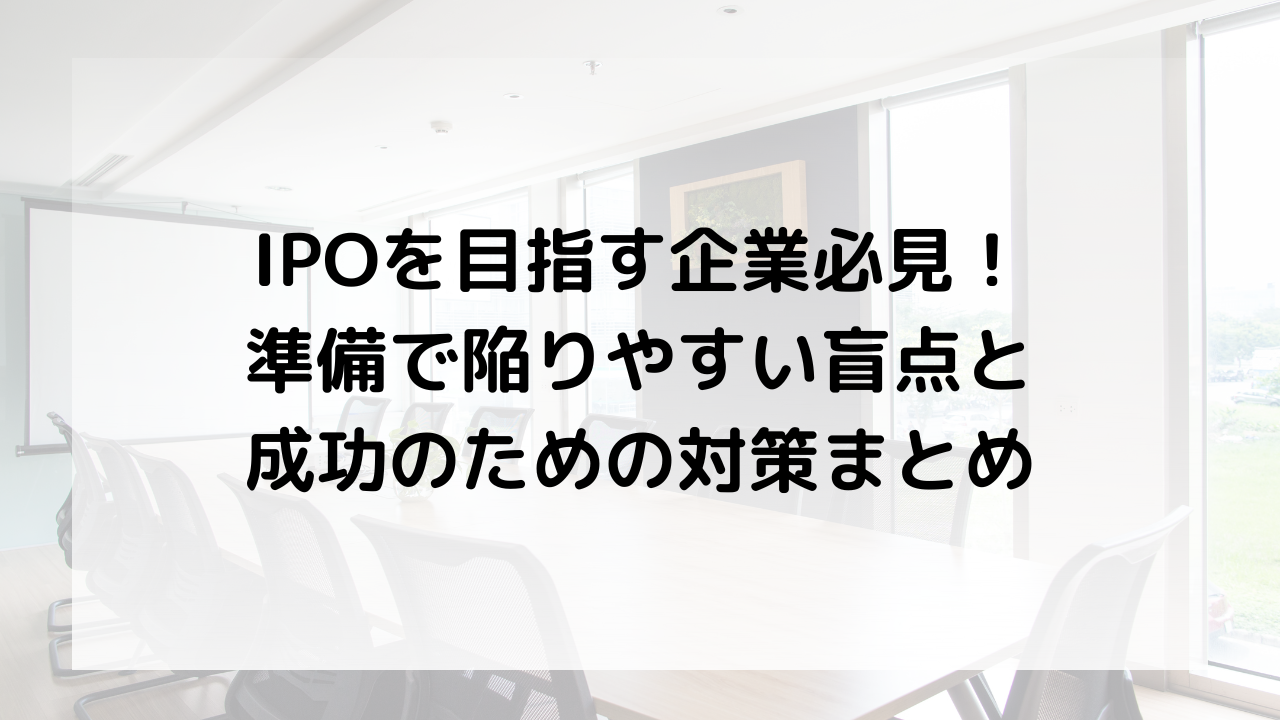トピックス
東証グロース市場とは?IPO準備で押さえるべき特徴と上場基準を徹底解説

はじめに
IPO(新規株式公開)を目指す企業にとって、「どの市場を選択するか」は極めて重要な戦略的判断です。上場により資金調達の選択肢が広がるだけでなく、社会的信用力が向上し、人材獲得や取引拡大にもつながります。その中でも、成長段階にあるベンチャー企業や中小企業にとって有力な選択肢が東証グロース市場です。本稿では、IPO準備を検討する経営者やご担当者の方々に向けて、東証グロース市場のコンセプト・特徴・上場基準を整理し、実務における留意点を税理士法人の立場から解説いたします。

東証グロース市場のコンセプトとは?
市場区分の再編とグロース市場の誕生
2022年4月、東京証券取引所は従来の市場区分を再編し、「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つに区分しました。これに伴い、旧マザーズ市場やJASDAQの一部はグロース市場へ移行しています。グロース市場は、高い成長可能性を有する企業が資金調達を通じてさらなる成長を目指す場として位置付けられています。
グロース市場の役割
- 成長段階にある企業が比較的早期に上場できる
- 投資家に「将来性ある企業」への投資機会を提供
- 社会全体としてスタートアップの成長を促進する仕組み
単なる上場の場にとどまらず、成長資金の循環を促進するプラットフォームとして機能しています。
東証グロース市場の特徴
- 上場基準が比較的緩やか
プライム市場やスタンダード市場と比べて財務基準が緩和されており、成長段階の企業でも挑戦しやすい環境です。
- 成長可能性に重点を置く審査
現時点での業績に加え、将来の成長戦略やビジネスモデルの持続可能性が重視されます。赤字企業であっても、成長性が評価されればIPO準備を進められる点が特徴です。
- 上場後も情報開示が重視される
上場時の基準は緩やかでも、上場後は四半期ごとの決算開示や内部統制の整備が求められます。そのため、IPO準備の早期段階からガバナンス体制を整えておく必要があります。
東証グロース市場の上場基準
IPOを実現するには、以下の基準を満たすことが必要です。
- 株主数:150人以上
- 流通株式数:1,000単位以上
- 流通株式比率:25%以上
- 時価総額:5億円以上
- 純資産額:正の数であること
プライム市場やスタンダード市場に比べ、基準は低めに設定されています。ただし、単に基準を満たすだけではなく、継続的に維持できる内部管理体制の整備が不可欠です。
東証グロース市場でIPOを目指すメリット
- 成長資金の調達が容易
株式市場からの資金調達により、研究開発や人材投資に充てることができます。
- 中小・ベンチャー企業に適した市場設計
黒字化前であっても、成長性が認められれば上場が可能となり、将来的な飛躍のきっかけとなります。
- 社会的信用力の向上
上場企業となることでブランド力が高まり、金融機関や取引先からの信頼度も向上します。採用、営業、資本提携など幅広い場面でメリットが得られます。
東証グロース市場でIPO準備に必要なステップ
IPO準備は通常2〜3年を要する中長期的なプロセスです。典型的な流れを整理すると、以下のとおりです。
- 財務・会計体制の整備
- 財務諸表の信頼性確保
- 税務リスクや不適切な会計処理の是正
- 税理士法人の支援による決算精度の向上
- 内部統制・ガバナンスの構築
- 取締役会の運営体制
- 監査役・社外取締役の配置
- 業務フローの明確化とリスク管理
- 主幹事証券・監査法人の選定
- 主幹事証券はIPO成否を左右する存在
- 監査法人は会計の適正性を担保
- 上場申請に向けた書類作成
- 有価証券報告書
- 内部管理報告書
- ガバナンス関連資料
IPO準備で直面しやすい課題とリスク
- 内部統制構築の遅れ
上場後に求められる開示・ガバナンス要件に遅れが生じると、不祥事リスクや株価下落を招く可能性があります。
- 人材不足
CFOや経理財務・内部監査人材の不足は多くの企業で課題となります。外部専門家の活用が必要です。
- 資金繰りの不安定さ
監査・コンサル費用など多額のコストがかかるため、資金計画を誤ると上場計画が頓挫するリスクがあります。
- ステークホルダー調整
株主やVC、従業員株主との調整を怠ると、IPO後のガバナンスに悪影響を及ぼします。
☞税理士法人などの専門家関与により、早期からの準備がリスク低減につながります。
IPO準備のタイムライン詳細
IPO準備は以下の3段階に分けられます。
【1年目】IPOの意思決定と基盤整備
- 経営陣での合意形成
- 主幹事証券・監査法人の選定
- 過去決算の見直し
- 内部統制構築の着手
【2年目】内部統制・管理体制の構築
- 内部統制の運用テスト
- 人材採用・配置
- 予算管理体制の確立
- IR活動の準備
【3年目】上場審査対応と最終調整
- 上場申請書類の作成
- 上場審査対応
- 投資家向け説明会(ロードショー)
- 上場承認・公開
最終段階では内部統制に関する詳細な説明資料提出が求められ、企業の状況によっては時間を要することもあります。
東証グロース市場と他市場の比較
IPO準備を進めるうえで「どの市場を選択するか」を明確にすることは非常に重要です。ここでは、グロース市場とプライム市場・スタンダード市場の違いを整理します。

☞グロース市場は「挑戦の場」、スタンダード市場は「安定の場」、プライム市場は「国際競争力を持つ大企業の場」と整理できます。企業の成長ステージに応じて、どの市場を狙うかを戦略的に決定することがIPO準備の第一歩です。
税理士法人が支援できるIPO準備のポイント
税理士法人はIPO準備において、以下のような実務支援を提供できます。
- 財務デューデリジェンス
決算の信頼性を確保し、上場審査に耐えうる財務基盤を整備します。
- 内部管理体制の整備支援
ガバナンス・内部統制の仕組みを導入し、透明性を高めます。
- 税務リスクの把握と改善
IPO準備段階で潜在的な税務リスクを洗い出し、上場後の不安要素を排除します。
- 他専門家との連携
弁護士・社会保険労務士などと協働し、総合的なIPO支援体制を構築します。
よくある質問(FAQ)

Q1. IPO準備はどのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的には2〜3年を要します。特に内部統制や監査対応といった体制整備には時間を要するため、早期の着手が望ましいといえます。当法人でも、計画段階から関与することで準備を効率的に進めるサポートを行っております。
Q2. 赤字でもIPOできますか?
A. 東証グロース市場では、成長可能性が重視されるため、赤字の段階でも上場は可能です。ただし、事業計画の合理性や資金繰りの見通しを明確に示す必要があり、財務面の整理が欠かせません。
Q3. 税理士に依頼するメリットは?
A. 財務・会計の透明性を高めることは、IPO審査において不可欠です。税理士法人が関与することで、会計処理の適正性や税務リスクの把握が可能となり、上場審査への対応力が格段に高まります。
Q4. IPO準備にはどのくらいの費用がかかりますか?
A. 監査法人や証券会社への報酬、内部統制の構築費用などを含めると、数千万円規模になるケースが一般的です。会社規模や業種によって差がありますので、事前に資金計画を立てることが重要です。
Q5. IPO準備を始めるベストなタイミングは?
A. 上場を目指す3年前からの準備開始が理想的です。特に決算体制や内部統制の整備には時間を要するため、可能な限り早期に取り組むことで、審査をスムーズに進めることができます。
Q6. 上場後に気をつけるべきことは何ですか?
A. 四半期ごとの情報開示、株主対応、IR活動などが求められます。特に投資家との信頼関係を継続的に築いていくことが重要であり、開示体制の維持が不可欠です。
Q7. IPO準備中に失敗しやすいポイントは?
A. 内部統制の整備が遅れることや、CFO・経理担当者などの人材確保が不十分なまま準備を進めてしまう点です。早期に人材を確保し、必要に応じて外部専門家を活用することが成功の鍵となります。
Q8. グロース市場に上場した後、他市場へ移行することは可能ですか?
A. 可能です。企業の成長段階に応じて、スタンダード市場やプライム市場への変更申請が行えます。ただし、その際にはより厳格な基準を満たす必要があるため、長期的な成長戦略を視野に入れた準備が求められます。
まとめ|IPO準備は東証グロース市場の理解とリスク対策から
IPOは企業成長を加速させる重要な経営戦略です。特に東証グロース市場は、成長企業が挑戦しやすい環境を備えています。ただし、IPO準備には内部統制の整備、人材確保、資金繰り管理、株主調整など多くの課題が伴います。
税理士法人の立場から強調すべき点
- IPO準備は最低2〜3年を要する長期プロジェクト
- 市場特性を理解し、自社のステージに合った市場選択を行うこと
- 税理士法人など専門家と早期連携することが成功への近道
当法人では、財務・会計から内部統制・ガバナンスまでトータルでIPO準備をご支援しております。IPOをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

共同代表
(公認会計士・税理士・CFP)
熊谷 和哉
2000年有限責任監査法人トーマツ入社、上場会社の会計監査とともに、会計基準対応・IPO支援・内部統制構築等アドバイザリー業務に従事
2021年、20年超所属したトーマツ退社後、これまでの経験・知見を活かして自らが主体となるべく、デロイト トーマツ出身者を中心とした税理士法人・会計コンサルティングファームであるコンフィアンスグループを設立し共同代表として参画